1860年の咸臨丸太平洋横断などで知られる勝海舟は,幕末において尊皇攘夷思想と対立したが,その対立は中国と朝鮮に対する認識にも及んでいた。尊王攘夷派は日本を特別な国とみなし,吉田松陰は,「朝鮮・満州・支那を切り随へ」と論じた。それに対して海舟は1863年の日記に,日本・朝鮮・中国の東アジア三国が同盟して欧米の侵略に抵抗する構想を記しているのである。
尊皇攘夷運動は倒幕運動へと発展し,明治維新によって明治政府が成立したが,明治政府の首脳は攘夷ではなく,文明開化の名のもと,欧米にならった近代国家建設を目指し,欧米の文化導入に努めた。その一方で,尊皇攘夷思想は欧米伝来のナショナリズム思想と奇妙に融合し,大日本帝国を神国とする極端なナショナリズム思想の源流となっていく。
しかし,海舟はそのような近代国家建設のあり方と,その手本となった欧米の近代文明のあり方にも批判の目を向けている。それが明確になるのは,日清戦争をめぐってであった。 日清戦争直前の1894年6月2日,李氏朝鮮への派兵決定と同時に当時の伊藤博文内閣は,イギリスとの不平等条約改正案に反対する衆議院を解散し,7月16日に改正条約に調印し,その2週間後に清朝に対して宣戦を布告した。宣戦布告後に行われた総選挙で選出された衆議院は,戦争のための政府協力でまとまり,改正条約調印を追認した。従って日清戦争開始は,当時の伊藤博文内閣にとって改正条約調印のための手段という側面を持っていた。また,日清戦争直前に日本が改正条約調印に成功し,イギリスから欧米的な近代国家として認められたことは,戦争遂行にとっても有利に作用した。日本は欧米的国際法さえ遵守すれば,帝国主義的侵略を行っている欧米諸国と同様に,「文明」国の一員として,「野蛮なる支那」と戦うことが可能となったのである。『学問のすゝめ』で知られる文明開化の旗振り役であり,既に「脱亜論」を発表して「亜細亜東方の悪友を謝絶せよ」と主張していた福沢諭吉は,「『文明』の『野蛮』に対する戦争」として日清戦争を正当化した。また,伊藤博文も「文明」国の一員として清朝との講和に臨んだ。清朝全権の李鴻章が,日本の領土要求は将来の日本と清朝の協力を困難にしてアジアに対する欧米列強の侵略を激化させるから撤回して欲しいという趣旨の覚え書きを送ったのを無視して領土要求を貫徹し,さらに1871年に締結された日清修交条規を改正して,欧米が清朝に押しつけた条約と同様な不平等条約としたのである。後の日露戦争で決定的になる,欧米の帝国主義列強の側にみずからを位置づける姿勢が,早くもここであらわれている。
幕末以来の東アジア三国同盟論者であった勝海舟は,日清戦争を「不義の戦争」として終始一貫して批判し,日清戦争勝利後も,領土要求は欧米列強の新たな侵略をまねくとする立場からこれに反対した。しかし,事態は李鴻章や海舟が憂慮した方向に向かっていった。日本公使の首謀した1895年の閔妃暗殺事件で,日本の大陸浪人に王宮で妃を暗殺された朝鮮国王の李太王は,翌1896年に日本の圧力を避けてロシア公使館に移った。この結果,日本が日清戦争の戦争目的に掲げた「朝鮮の独立」は,ロシアの朝鮮への影響力増大という,日本にとって最悪の形で破綻した。同年ニコライ2世の戴冠式に出席した李鴻章はヴィッテと協議し,日本の攻撃に対する共同防衛を密約してロシアに東清鉄道の付設権を認めたため,日本は東アジア三国の中で孤立した。そして1897年のドイツの膠州湾武力占領を皮切りに1899年にかけて,列強の中国分割競争が激化したのである。
1898年勝海舟のもとを,戊戌政変で敗れ日本に亡命した康有為と梁啓超が訪れた。海舟は忠告書を渡し,性急な改革の失敗の必然と,外国の援助に頼って自国の改革を行うことの愚を説き,日本の真似をするのではなく,中国の社会に即した改革を行う必要性を強調した。その数ヶ月後,海舟は「コレデオシマイ」という有名な臨終の言葉を残してこの世を去るが,その後の日本を含む東アジアの歴史は,おそらく海舟がもっとも望まなかった形で展開していくことになる。
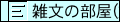 へ戻る
へ戻る
 トップへ戻る
トップへ戻る